音楽クリエイターとして、著作権管理の方法を選ぶことは、創作の自由や収益、作品の長期的なコントロールに大きな影響を与える重要な決断。日本で最も有名な著作権管理団体の一つであるJASRAC(日本音楽著作権協会)だが、自分はそのサービスを利用しないことを選んだ。その理由を以下にまとめる。
目次
1. 楽曲ごとの柔軟性がない
JASRACと「著作権信託契約」を結ぶと、過去および将来の全ての作品を一括して管理委託する必要がある。個別の楽曲を独立して管理することはできない。一部の作品を自分でコントロールしたい場合や、異なるライセンスモデルを試したい場合には、この一括管理は大きな障壁となる。
2. 長期的な契約と限定的な解約オプション
JASRACの契約期間は、著作者の死後70年まで続く著作権保護期間全体に及ぶことが一般的。一度契約すると、状況が変わったりサービスに不満があった場合でも、権利を回復したり契約を終了することが非常に困難。この柔軟性の欠如は、クリエイターにとって不合理と感じられる場合がある。
3. 複雑な手続きと事務負担
多くのクリエイターが、JASRACの登録プロセスやシステム全体が煩雑で理解しづらいと感じている。特に独立系の音楽クリエイターは、作品登録や無断使用に関する紛争処理で困難を経験している。シンプルさや効率性を求める人々には、大きな障害となり得る。
4. ライセンス決定権の制限
作品をJASRACに委託すると、その使用許諾やライセンス方法はJASRACが管理することになる。これによりロイヤリティ収集が効率化される一方で、映画やCMでの使用(シンクロ権)など、自分で特定の取引を交渉したい場合には制限される。この集中管理方式は、一部のクリエイターには不自由に感じられる。
5. 透明性への懸念
JASRACによるロイヤリティ分配や契約条件については透明性への疑問が寄せられている。多くのクリエイターが、ロイヤリティがどのように計算・分配されているかについて明確な説明を受けていないと感じている。また、一部の契約内容はクリエイターよりも出版社など他の利害関係者に有利だという指摘もある。
6. 代替手段の存在
日本ではNexToneなど、個別作品ごとに登録できる柔軟な選択肢を提供する団体も存在する。より自律的でカスタマイズされたソリューションを求めるクリエイターには、これらの代替手段が適している可能性が高い。
結論
JASRACは、多くのクリエイターにとってロイヤリティ収集や知的財産保護を簡素化する有用なサービスを提供している。しかし、その一律的なアプローチは、独立系音楽クリエイターとして目指す方向性には合致しない。柔軟性や長期契約による制限、事務負担、ライセンス決定権への制限など、そのデメリットがメリットを上回る。
JASRACや類似団体を検討する際には、契約内容を慎重に確認し、自身の創作ビジョンやビジネスニーズに合った選択肢を探すことが重要だと思う。
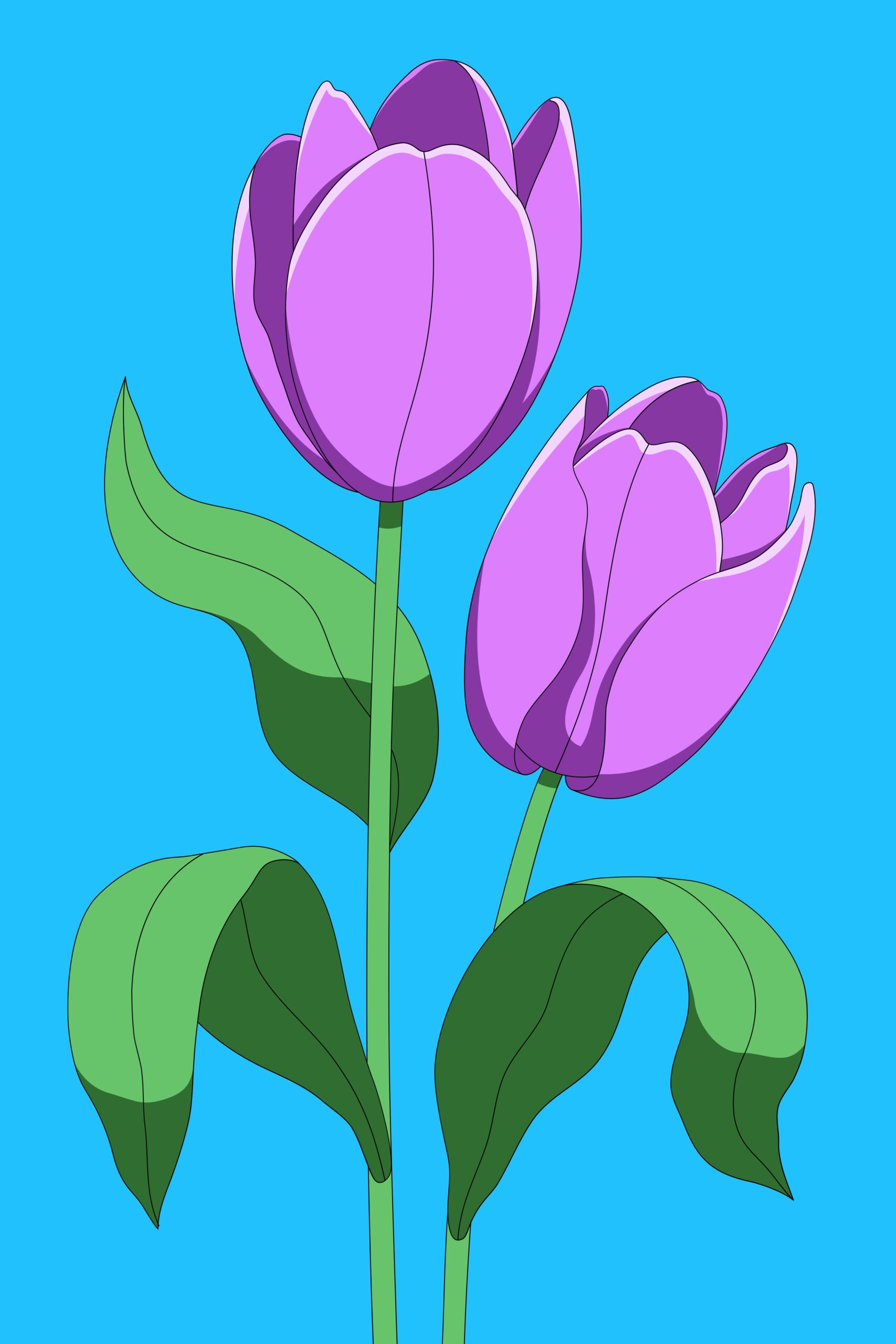
コメントを残す