デジタルガーデンは、従来のブログとは異なる新しい形のオンライン知識共有スペースです。時系列に沿った記事投稿ではなく、アイデアや知識を有機的に成長させ、相互にリンクで結びつけながら育てていく個人的なデジタル空間を指します。
基本概念と特徴
デジタルガーデンは「メモを取る方法を説明する比喩」として生まれた概念で、実際の庭園のように何かが育つ場所として機能します。個人的でありながら公開されており、訪問者は予期しない発見や洞察に出会うことができる空間です。
時系列よりも文脈的関係を重視し、相互リンクを使ってコンテンツを管理するのが大きな特徴です3。ブログのように新しい記事が古い記事を押し下げるのではなく、すべてのコンテンツが等しく価値を持ち続けます。
デジタルガーデンの6つの特徴
Maggie Appletonが整理したデジタルガーデンの主要な特徴は以下の通りです:
地形的構造(Topography over Timelines) – 時系列ではなく、文脈的な関係や連想によるリンクを重視し、相互リンクでコンテンツを管理します。
継続的成長(Continuous Growth) – 静的で更新されないものではなく、継続的に内容を更新し、コンテンツ全体の進化を促進します。
不完全性と公開学習(Imperfection & Learning in Public) – 不完全であることを許容し、学習過程にあるものを積極的に共有します。
遊び心と個人性(Playful, Personal, and Experimental) – 画一的な作りではなく、自分に合わせた独自の表現を構築します。
多様なコンテンツ形態(Intercropping & Content Diversity) – テキストだけでなく、音声や動画など様々な種類のコンテンツを受け入れます。
独立した所有権(Independent Ownership) – 企業プラットフォームから独立して、長期的に自分のデジタル空間を管理します。
ブログとの違い
従来のブログとデジタルガーデンには明確な違いがあります。ブログでは「大勢の聴衆に向けて話す」のに対し、デジタルガーデンでは「自分自身と対話している」状態で、時間をかけて育てたいものに集中します。
デジタルガーデンでは成長と変化が可能であり、同じトピックに関するさまざまなページが共存できることが重要な特徴です。日本庭園が「完成しない芸術」と呼ばれるように、デジタルガーデンも常に進化し続ける空間として設計されています。
構築方法とツール
デジタルガーデンの構築には様々な選択肢があります。コードを書かずに実現する場合は、ObsidianやNotion、Roam Research、Logseqなどのツールが利用できます。国内のサービスではScrapboxも選択肢として挙げられます。
より自分に合った形を作り上げたい場合は、HTMLやCSS、JavaScriptを直接書いて独自のシステムを構築することも可能です。
Wikiとの関係
デジタルガーデンは各コンテンツをリンクで結びつけて全体を構成するため、Wikiと非常に似ています。実際、「庭」という表現を最初に使ったMike CaulfieldはWikiWikiの発明者Ward Cunninghamと一緒にパーソナルWikiの利用について研究していたとされており、デジタルガーデンの概念的なルーツはWikiにあると考えられています。
デジタルガーデンは、ライフログのような個人記録とブログのような主張の中間に位置し、様々な情報を公の場に置きながら、訪問者が自由に探索できる環境を提供しています。
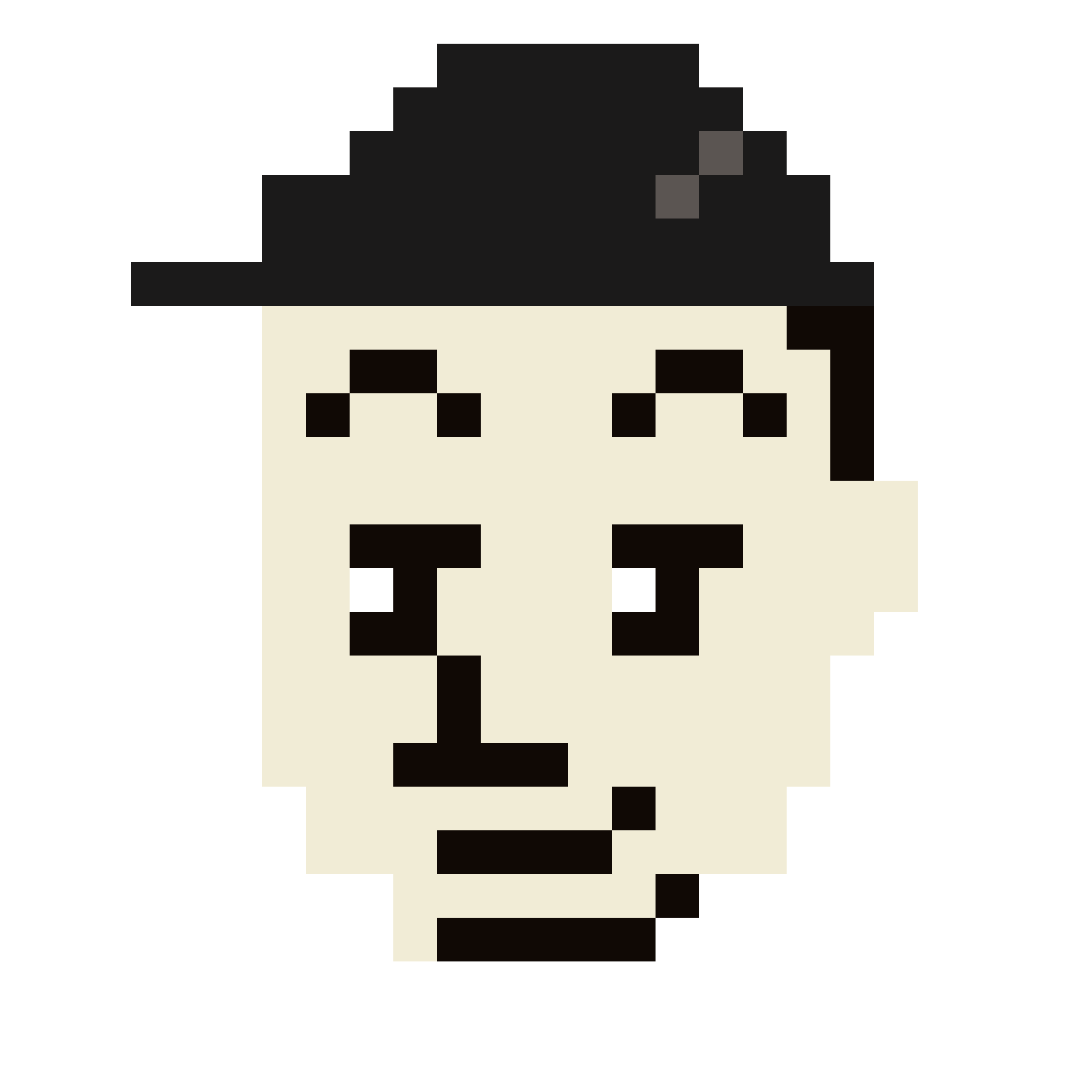
寄付する