 ラッパーのマインドセット
ラッパーのマインドセット 自信を高めるために:ラッパーのための「劣等感」との向き合い方
ラッパーとして活動していると、楽曲のリリースやライブ、リスナーとの反応まで、日々いろんな感情が押し寄せてくる。ときには「自分はまだまだだ」と感じて、なかなか曲を出せなかったり、セルフプロモーションに躊躇してしまうこともあるだろう。その「劣等...
 ラッパーのマインドセット
ラッパーのマインドセット  Suno
Suno  AIビートメイク
AIビートメイク  AIビートメイク
AIビートメイク  音楽配信
音楽配信  ラッパーのマーケティング
ラッパーのマーケティング  ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル 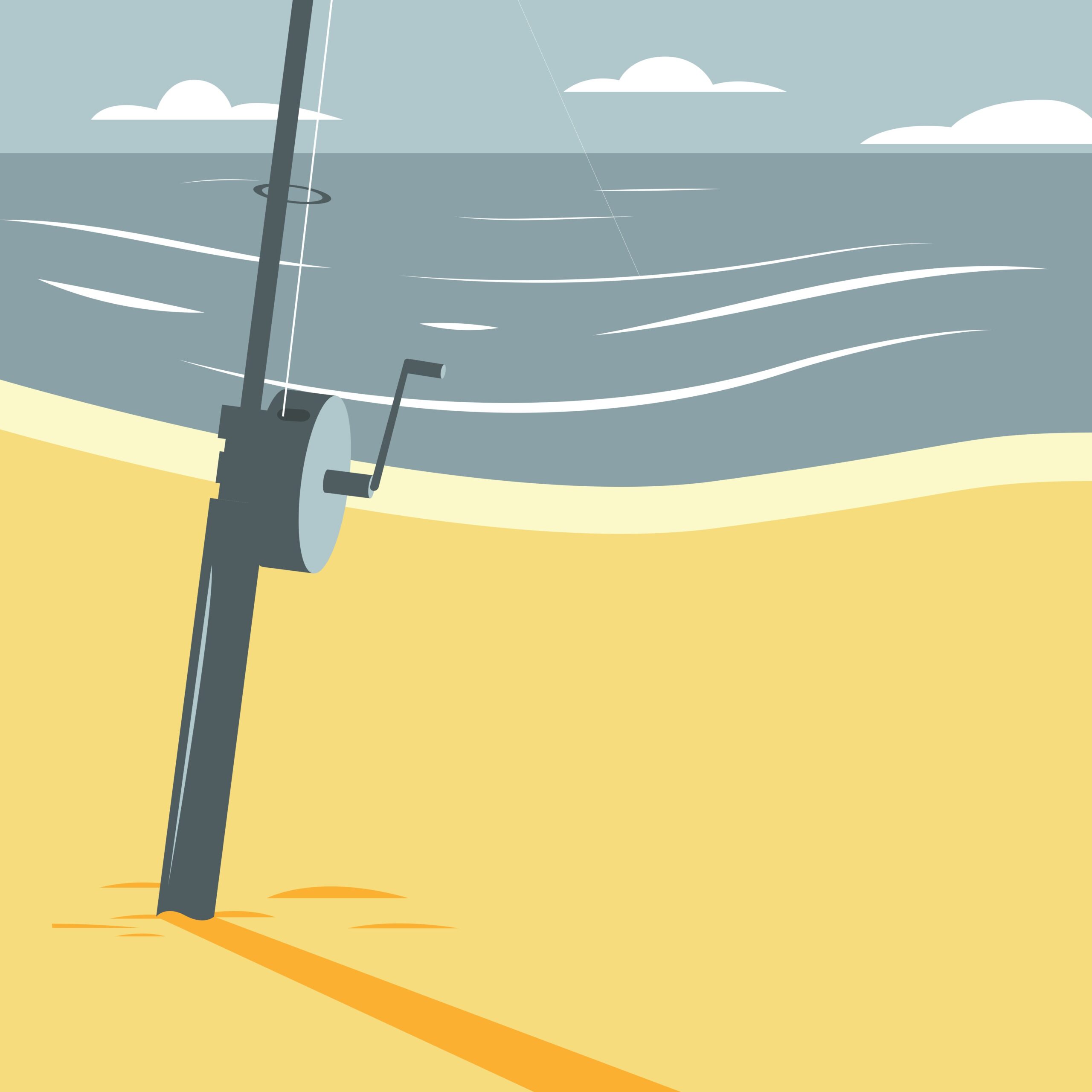 ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル 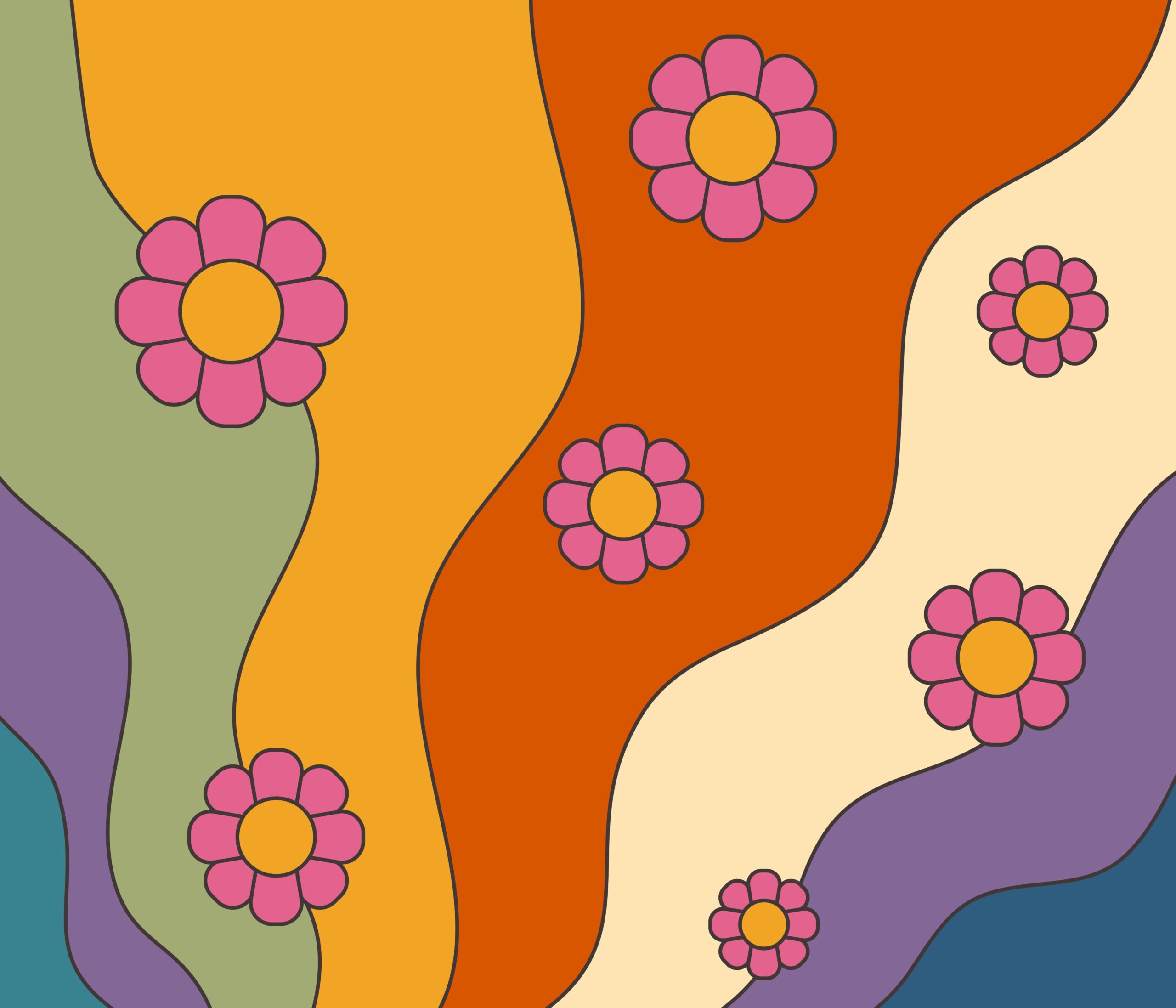 ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル  ラッパーのマーケティング
ラッパーのマーケティング  ラッパーのマインドセット
ラッパーのマインドセット  音楽配信
音楽配信  ラッパーのマーケティング
ラッパーのマーケティング 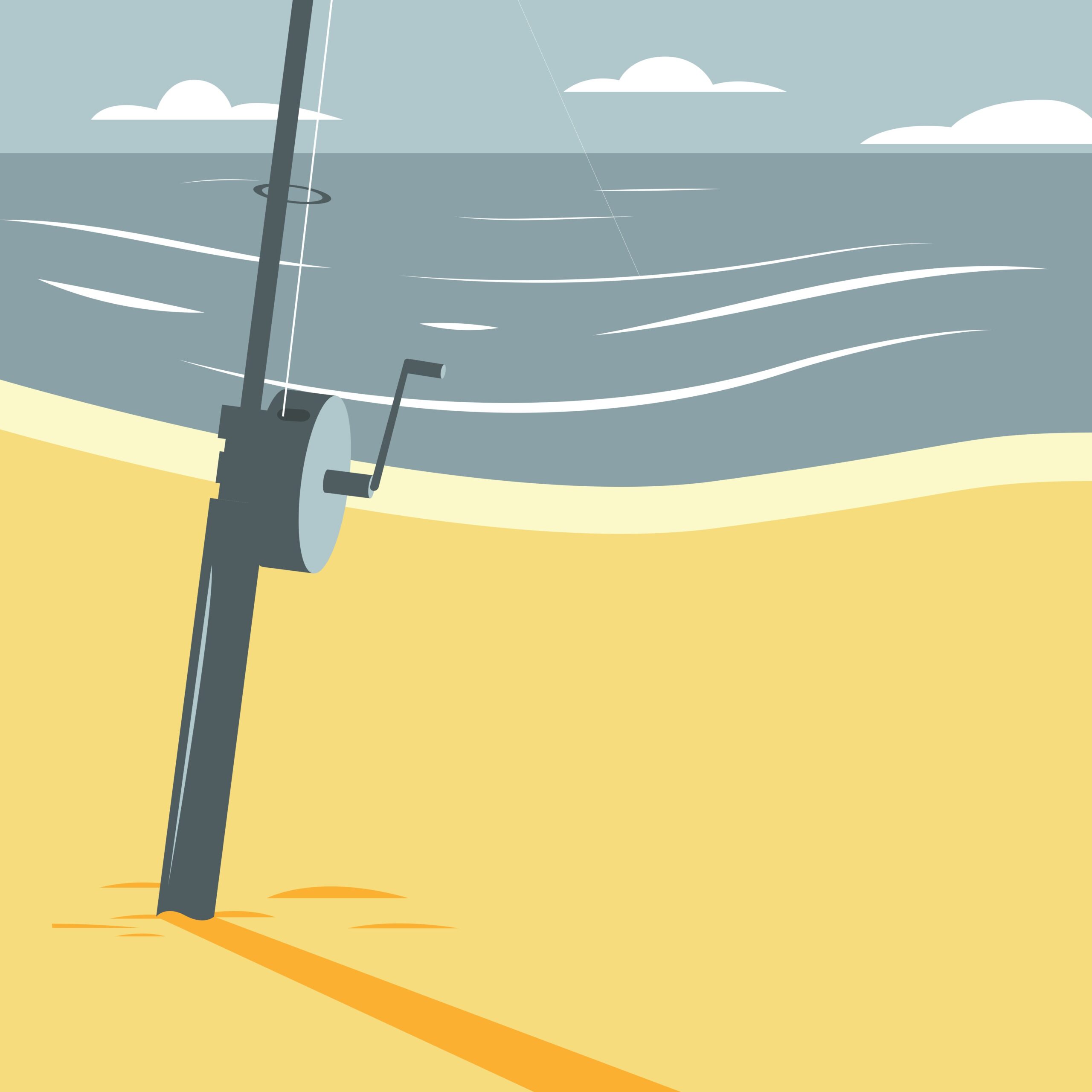 ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル  ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル 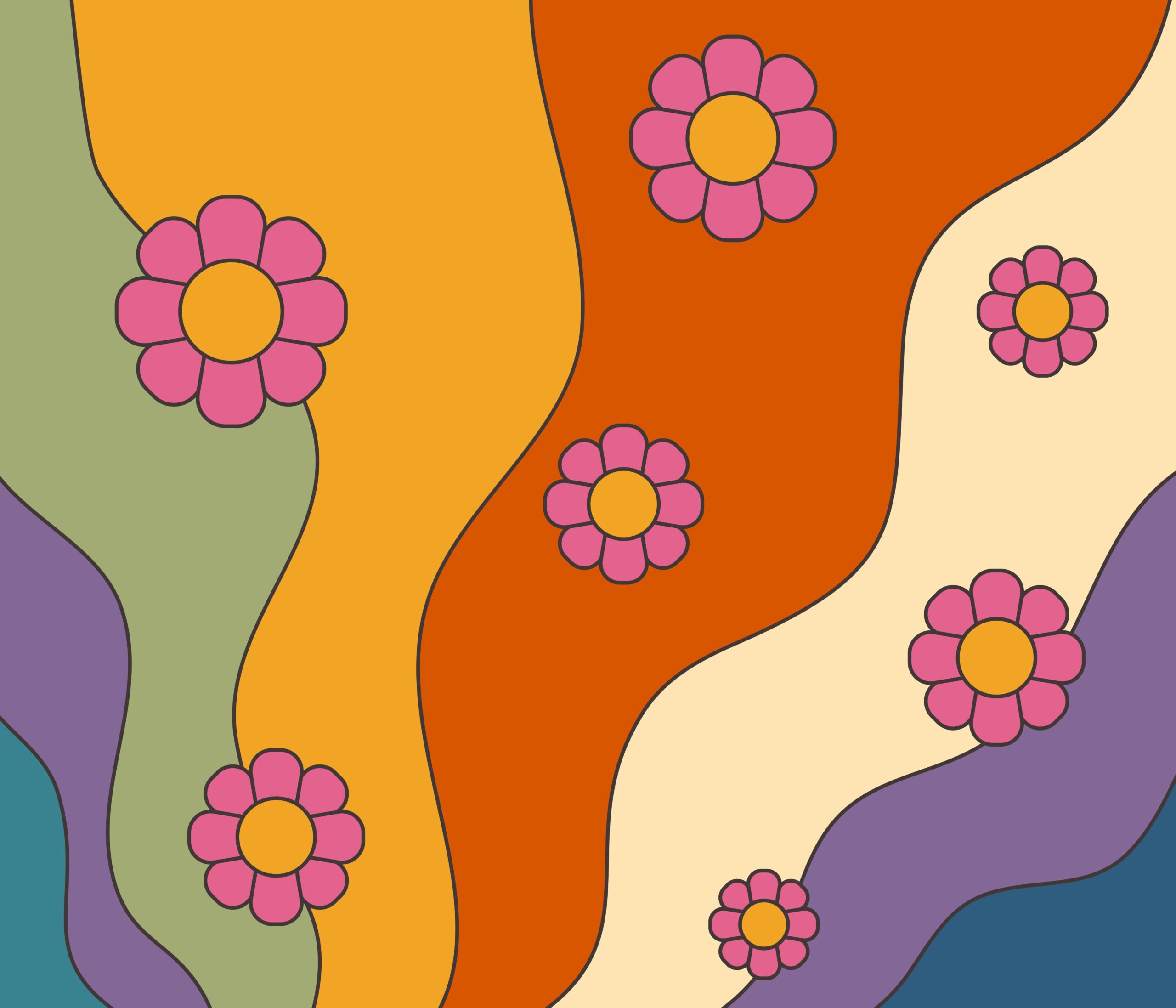 ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル  ラッパーのマーケティング
ラッパーのマーケティング  ラッパーのマーケティング
ラッパーのマーケティング  ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル  ラップ・ボーカル
ラップ・ボーカル  エモいヒップホップビート
エモいヒップホップビート  ブーンバップヒップホップビート
ブーンバップヒップホップビート  ダークヒップホップビート
ダークヒップホップビート  ハッピーヒップホップビート
ハッピーヒップホップビート  ハッピーヒップホップビート
ハッピーヒップホップビート  ハッピーヒップホップビート
ハッピーヒップホップビート  エモいヒップホップビート
エモいヒップホップビート 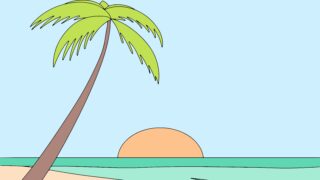 エモいヒップホップビート
エモいヒップホップビート  エモいヒップホップビート
エモいヒップホップビート  ダークヒップホップビート
ダークヒップホップビート